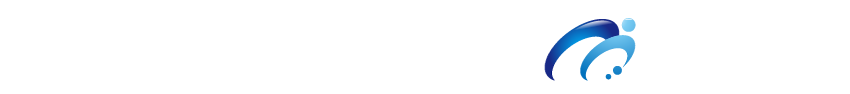目次
1. 保守管理の過酷な環境と高リスク
近年、日本の夏は気温・湿度ともに上昇傾向にあり、水処理メンテナンスの現場でも過酷な環境が常態化しています。
屋外、地下、また工場では空調停止中であったり、建設現場では空調未整備という状況であったりすることが多く、
缶体内や水槽内部など密閉空間で作業する場合は、周囲より数℃上昇し蒸し暑くなることも珍しくありません。
このような場では、酸欠や有害ガス中毒に加えて、熱中症リスクが極めて高まると考えられます。
2. 法規制と義務化された対策体制
2025年6月1日、熱中症対策が労働安全衛生規則で義務化されました。
WBGT値(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上で一定時間作業が想定される場合、事業者には以下の体制整備・手順作成・関係者周知が求められます。
これは単なる努力義務ではなく、違反時には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用される可能性もある企業にとって重大な法的責任となります 。
参考:厚生労働省│職場における熱中症対策の強化について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)
3. 熱中症の基礎知識と職場における見逃せない現象
厚生労働省によると、熱中症は高温多湿下での体温調整機能の失調によって引き起こされる障害で、主な症状は下記のように分類されます。
| 区分 | 主な症状 |
|---|---|
| 軽度 | めまい・立ちくらみ・こむら返り(筋肉のけいれん)・大量の発汗 |
| 中度 | 頭痛・吐き気・嘔吐・全身のだるさ(倦怠感) |
| 重度 | 意識障害・けいれん・体温上昇(高体温:40℃前後) |
このように段階別に症状を把握し、早期発見・早期対応することが重要です。
水処理現場では、密閉空間での作業中にこうした症状が発生すると、酸欠や溺水のリスクも増し、初動の遅れが命に関わる事態につながりかねません。
4. 現場で実践すべき具体策(予防・応急・教育)
WBGT(暑さ指数)の導入と見える化
WBGT計を常設し、作業場所の暑さをリアルタイムで監視できるようにしましょう。
その値に応じて、休憩頻度や作業量を調整することが重要です。電子掲示板やアプリによる通知も有効です。
水分・塩分補給のルール化
30〜60分ごとに水分・塩分補給タイムを設け、冷水や経口補水液、塩飴等を作業場所に常備しましょう。自覚症状の有無にかかわらず、定期的な補給が必要です。
また、作業場所のWBGT値が基準値を超える場合は特に、積極的な水分・塩分の摂取が重要です。
作業スケジュールの見直し(暑熱順化も含む)
梅雨明けから一気に気温の上昇が想定されるため、6月初旬から徐々に作業時間を延ばし、熱への順化期間を設けましょう。
屋外作業に慣れていない人や高齢の作業員の方は特に配慮が必要です。
猛暑日には、屋外作業を早朝や夕方にシフトするなどの工夫が推奨されています。
服装・環境改善機器の導入
空調服、冷却ベスト、冷感タオルなどの装備。
屋外現場では扇風機、ミスト機、遮光ネット、スポットクーラーの設置が効果的です。
前泊・人員余裕の確保
寝不足・疲労状態での作業は危険を伴います。安全を確保するためには交代要員の準備だけではなく、必要に応じて現場近くでの前泊を推奨します。
高リスク環境では、人数が少ないと作業中の異変に気付きにくく、対処が遅れがちです。
応急対応の整備と周知
- 作業を中止し、涼しい場所へ移動
- 首・脇・足の付け根に保冷剤を当て、風を送る気化冷却を実施
- 意識がある場合は経口補水液等で水分補給を行う
- 意識障害やけいれんがある場合は即119番通報・搬送
- 事後は労災申請や社内報告を行う
PDCAサイクルでの継続的改善
導入・実施後は記録と分析をしたうえで、今後の改善策を反映する体制づくりが重要です。
補助制度の活用(高年齢労働者向け)
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」では、60歳以上就労労働者の安全対策として、WBGT指数計やスポットクーラー、空調服などの導入費用が補助対象となる場合があります。
こうした制度は積極的に活用したいものですね。
参考:厚生労働省│「令和7年度エイジフレンドリー補助金」のご案内
5. 水処理現場における熱中症対策のポイント
- 屋外や密閉空間での作業中のWBGT管理:水槽・缶体内部は外気より数度高温湿。外部計測だけでは正確に測れないこともあるため、内部計測器の導入が望ましい。
- 酸欠・有毒ガスとの複合リスク:高熱環境下での有害ガス中毒の兆候と熱中症症状が重なると、初動判断が難しくなるため、より厳密な体調観察が必要です。
- 営業・工程計画からのリスク共有:作業人員や宿泊の調整は工程確定後では難しいため、営業担当が計画段階から現場条件をお客様と共有しておくことが重要です。「スケジュール調整」「余裕のある作業員数の確保」「冷却機材」の必要性を含めて工程の協議を行うことで、発注者・作業者双方にとって安心・安全な計画が可能になります。
6. なぜここまで対策が重要なのか
厚労省によれば、熱中症による労災死亡事案は他の労働災害の5〜6倍に及び、死亡者の約70%が屋外作業中に発症しているとされています。熱中症の死亡災害の傾向として、「初期症状の放置、対応の遅れ」が顕著であり、組織的・計画的対策が不可欠なのです。
参考:職場における熱中症対策について
また、災害後の労災認定は、WBGT把握状況・予防措置・報告体制の有無など、事業主側の対応の有無が大きく審査に影響する可能性がありますします note(ノート)厚生労働省。
7. 現場と営業が連携して事前の備えを徹底
- WBGT等による暑さモニタリング+見える化
- 定時の水分・塩分補給ルール
- 作業計画の暑熱順化・前倒し・前泊
- 冷却機器・資材の整備
- 人員余裕と観察強化
- 応急対応マニュアルの現場共有と訓練
- PDCAでの継続改善
- 制度補助の活用
- 営業からお客様へのリスク説明と契約段階での調整
猛暑の中でも安全かつ効率的に成果を出すためには、現場を熟知した営業担当が交渉段階から熱中症リスクを考慮した提案を行うことが鍵となります。
お客様と事前にリスクを共有し、余裕のある工程を組むことで、現場と発注者双方が安心してプロジェクトを進められるのです。
工程立案から熱中症対策を組み込むことは、法令遵守であるだけでなく、「人命」「企業信頼」「生産性」を一体的に守る投資とも言えるでしょう。