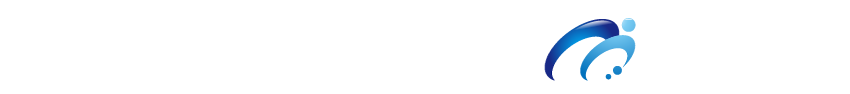工場は、製造業の企業にとって「利益を生み出す場所」であり、まさに企業活動の心臓部です。製品や商品を製造するためのエネルギーや水は欠かせませんが、それらをどのように効率よく使うかによって利益率は大きく変わってきます。
近年は、電気・ガス・水道といった光熱費が高騰し続けています。特に水道料金は全国的に値上げの動きが広がっており、水を大量に使う工場にとっては経営を圧迫する大きな要因となっています。また、地球温暖化対策としてのカーボンニュートラルやSDGsの達成が強く叫ばれており、工場の省エネ化は「コスト削減」だけではなく「社会的責任」を果たすための重要な取り組みでもあります。
こうした背景の中で、工場の省エネをどう実現するかは、多くの企業にとって喫緊の課題です。
※本記事は、2018年8月31日公開の「コストダウンにつながる工場の省エネテクニックをご存知ですか?」をベースに、現在の情勢を元に再編集したものです。旧記事はこちら。
目次
工場での電力と燃料の省エネ
”工場”と一口に言っても生産品目や稼働状況、工場の規模などによりエネルギーの使い方や使用量はそれぞれ異なりますが、以下に一例をご紹介します。
エネルギーの内訳(電力と燃料)
工場の電力使用は、照明や空調設備、製造機械の動力など、多岐にわたります。古い設備を使い続けると、効率が落ちるだけでなく電力ロスが増加し、結果的にコストが膨らみます。
そのため、最新のLED照明や高効率空調への更新、IoTやAIによる稼働状況の自動制御といった取り組みが効果的です。さらに、従業員一人ひとりが「使用しない時はこまめに消灯する」「空調の設定温度を適正に保つ」といった省エネ行動を徹底することで、小さな積み重ねが大きな効果につながります。

燃料(ガスや石油)は、ボイラーや加熱炉などの稼働に不可欠です。ここでも、省エネ性の高い最新機器に更新することや、重油から都市ガス、さらには水素やバイオマスへの燃料転換によって、大幅な効率改善が可能です。
これらは初期投資が必要ですが、近年は補助金制度の充実により、企業の負担を大きく軽減できるようになっています。
工場での省エネの取り組み方
長期的にみれば、コスト削減効果が見込まれる場合でも、初期投資が高額になってしまったり、工場の作業効率に影響が生じたりする場合には、省エネへの取り組みは困難になります。費用対効果や製品の品質への影響、従業員への負担、満足度などを総合的に判断して、導入を検討する必要があります。
逆に言えば、導入コストが少なく、工場での作業方法に影響が生じない省エネ方法は、デメリットがほとんどないため、多くの工場において優先的に導入していきたい省エネ方法と言えるのではないでしょうか。
工場での水の省エネとは
続いて、工場において不可欠な水の省エネについてご紹介いたします。
工場における水資源について
工場では一日に数千トンもの水を使用することも珍しくありません。製造工程における原料水、冷却水、洗浄水、さらには散水や従業員の飲料水まで、幅広い用途で水は消費されています。
上水道をそのまま使用すれば、当然ながら水道料金は高額になります。また、冷却水や散水に使った水はそのまま排水されるため、無駄なコストが発生するケースも多くあります。
水を確保する
こうした課題を解決するために、工場では以下のような水資源の活用方法が広がっています。
地下水の利用
工場の敷地内に井戸を掘り、地下水を製造用水や冷却水として利用します。地下水は年間を通じて水温が安定しているため、冷却効率が高まり、省エネ効果も期待できます。オンサイト方式の導入
井戸掘削や浄水設備の設置を業者が負担し、工場側は使用した水の従量料金を支払う仕組みです。初期投資が不要で、導入リスクもゼロ。メンテナンス費や薬品代も従量料金に含まれるため、確実にコスト削減を実現できます。雨水や排水の再利用
工場の屋根に降った雨水をタンクに貯め、夏場の屋根散水や洗浄水に活用する事例もあります。また、排水を高度処理して再利用することで、取水量を削減しつつ排水処理費用も圧縮できます。
工場での水の省エネ対策事例
工場での水に関する省エネ対策事例を紹介します。
【大阪府】自動車部品工場様 製造用水向け 新規井戸設備
自動車部品工場(大阪府)
導入内容:新規井戸設備を導入し、コージェネ冷却水やボイラー用水に活用
効果:使用水量3,000㎥/月で年間約250万円のコスト削減
副次的メリット:井戸水の安定水温で冷却効率が向上、非常時には「災害時協力井戸」として地域に生活用水を提供
このように、省エネやコスト削減だけでなく、地域防災や社会貢献にもつながる事例が増えています。
引用:導入実績|ミズカラ株式会社 https://www.atss.co.jp/cases/006/
省エネ対策、水道代のコストダウン以外のメリットとしては、上水道以外の水源を確保することで、非常時(上水道断水時)に第二水源として使用することができます。
ちなみにこちらの工場は、非常時には近隣の被災者へ生活用水として水の提供を行う施設として、「災害時協力井戸」として大阪府に登録されております。地域貢献にもなっているということですね。
参考:大阪府/災害時協力井戸について
まとめ
工場の省エネ化は、電力・燃料の効率化だけでは不十分です。水の使い方を見直し、経営効率と環境対策を同時に実現できます。省エネは単なるコストダウンにとどまらず、企業の社会的価値を高め、災害時のレジリエンス向上にもつながります。2025年の今こそ、自社工場の省エネ戦略を「水・エネルギー」で再設計してみてはいかがでしょうか。