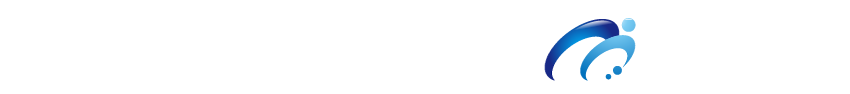目次
資源でもあり”リスク”ともなる水 企業活動に忍び寄る“水の異常”
近年、日本では極端な降雨パターンが頻発しています。1日の総降水量が200mmを超えた日数は、過去100年で約1.7倍に、また1時間あたりの降雨量が50mm以上となった頻度も約1.4倍に増加するなど、いわゆる”ゲリラ豪雨”による影響を各地で受けていることは顕著です。
参照:国土交通白書 2022 気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化
こうした異常気象により、企業は水害だけでなく、取水制限や排水機能不全といった“水の両極端”に備える必要性が増してきていることは明らかです。
② 気候変動による水災リスク: 豪雨・渇水・水没
- 豪雨・浸水リスク:2018年に西日本を中心に発生した西日本豪雨では、中小企業における被害額は4,738億円に上るとされており、また219年に千葉県を中心とする関東を襲った台風19号では、製造業、小売、運輸業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融業等の様々な産業に、営業停止など大きな影響をもたらしました。
参照:
経済産業省 中小企業の防災・減災対策に関する現状と課題について
国土交通省 令和元年台風第19号による被害等 - 取水制限・渇水:特定河川や井戸取水に依存する企業は、渇水や制限発令時に操業停止のリスクが高まります。また、操業停止とまではならずとも、工業用水の制限による生産活動の縮小、冷却水不足による設備故障のおそれ、製品の品質低下や製造工程を見直さざるを得なくなるなど、様々な影響を受けることが考えられます。
- 排水機能障害:豪雨時、排水先河川が氾濫・水位上昇すれば、企業排水が逆流したり排水不能となるケースも相次いでいます。
③ 見える化された”水リスク”と企業の脆弱性
国土交通省の浸水想定区域図や地域ハザードマップは、企業の拠点ごとの浸水深推定や取水制限の有無を把握するうえで非常に役立ちます。
参照:環境省 改訂版 民間企業の気候変動適応ガイド
ただ、多くの企業では浸水リスクの認識が十分浸透しておらず、地震対策に比べて水害対策は後回しになってしまっている企業も少なくないでしょう。
④ 水リスクを整理:企業が備えるべき4つの視点
| リスクの種類 | 内容と影響の例 |
| 取水リスク | 地下水や河川依存の施設で発生:渇水による操業停止、取水水質悪化 |
| 排水リスク | 排水先河川の逆流・排水機能不全による施設浸水や汚染 |
| 浸水リスク | 拠点が浸水し、設備停止・火災・電源喪失の可能性 |
| 風評リスク | 被災後の取引先信用低下や地域連携への影響 |
⑤ 企業が取り組むべき実践対策&事例
- ハザードマップと現地調査の併用:地図だけに頼らず、嵩上げ・排水ポンプの位置・電源位置を現地確認。
- リスク分散型設備の導入:高床式ポンプ室、雨水タンクと非常用井戸の併設など。
- 取水源の多様化:複数の水源確保で、一つの取水源停止時にも対応可。
- 例:非常用井戸+自治体水支援協定など。
- BCPに水災リスクを取り込む:割当水量想定、汎用代替スケジュール設定、緊急時対応手順の定義。
- 自治体連携と訓練活用:自治体の防災訓練やハザード情報共有、協定締結による早期避難・対応。
⑥業種別の水リスクの傾向
すべての企業が等しく水リスクに直面しているわけではありません。
業種や事業形態によって、その影響度は大きく異なります。特に以下のような業種では、水に対する依存度が高いため、水不足や水害が事業継続に与えるインパクトが大きくなります。
- 製造業(とくに食品・化学・金属加工)
工程水や冷却水として多量の水を使用するため、水源の安定性や水質の変化は生産ラインに直結します。
加えて、設備の水没や冠水による操業停止リスクも無視できません。 - 病院・介護施設などの医療福祉分野
安定的な水供給が生命・衛生に直結するため、断水や水圧低下がサービス提供に深刻な支障をきたします。
バックアップ水源の確保が急務とされます。 - 宿泊業・温浴施設・レジャー施設
顧客サービスにおいて“水”そのものが商品価値となる業種では、水質異常や供給停止は即クレームや営業損失につながります。
水道料金の高騰も経営を圧迫する要因です。 - 物流・倉庫業・流通センター
雨水や高潮による浸水被害が在庫・機材に直結するため、施設立地や排水インフラの見直しが求められます。
地下ピットや電源系統の水没リスクにも注意が必要です。
さらに、地方に拠点を構える中小企業では、地場の水道インフラの老朽化や更新遅延の影響を受けやすく、対策の差がそのまま事業継続の明暗を分けるケースも増えています。
こうした業種ごとの水リスクを見極め、自社にとっての「最適な備え」を考えることが、これからのBCPやインフラ戦略に不可欠です。
⑦「気候変動適応」としての水リスク管理の重要性
気候変動による影響は、もはや将来の懸念ではなく、すでに企業活動の現場で現実となっています。温暖化による海面上昇や猛暑に加え、近年では極端な降雨、渇水、水害といった“水のかたちをしたリスク”が顕在化しています。
こうした変化に向き合うためには、「緩和(mitigation)」と「適応(adaptation)」という二つのアプローチが求められます。
前者は脱炭素や温室効果ガス削減といった温暖化の進行を抑える取り組み、後者はすでに進行している気候変動の影響に備える取り組みのことを指します。水の供給体制や利用方法に伴うリスクへの備えは、この「適応」において中心的なテーマのひとつです。
また、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やCDP(国際的な環境情報開示プラットフォーム)の枠組みでは、水リスクが明確に開示対象として求められています。
たとえば以下の項目は、ESG報告や統合報告書において記載を求められるケースが増えています。
- 洪水・渇水による操業停止のリスク評価
- 原材料やサプライチェーンの水リスク
- 水資源使用量と代替手段の確保
実際に、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)も水資源の持続可能な利用をESG評価の重要項目として位置づけており、「水リスクを軽視する企業は投資対象としての魅力を損なう可能性がある」と明言しています
参照:年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF ESGリポート2023。
つまり、水リスク管理は単なる災害対策にとどまらず、中長期的な経営戦略や投資家からの信頼確保にも直結します。
企業規模や業種を問わず、水への備えは“選ばれる企業”であり続けるための条件のひとつと言えるでしょう。
⑧持続可能な経営のために、いまできる備えを
水害や渇水リスクは、気候変動の進行とともに確実に増しています。拠点ごとの水リスクを“見える化”し、自治体や設備ベンダーと連携して事前の備えを講じることは、企業のレジリエンスを高める有効な手段です。
そして、こうした事前対策はコストではなく、事業の継続性と企業の信用を守るための投資です。水にまつわる脅威を経営課題として正面から捉えることが、持続可能な企業活動を実現する第一歩となります。