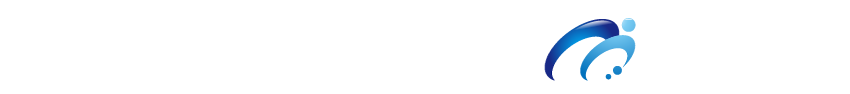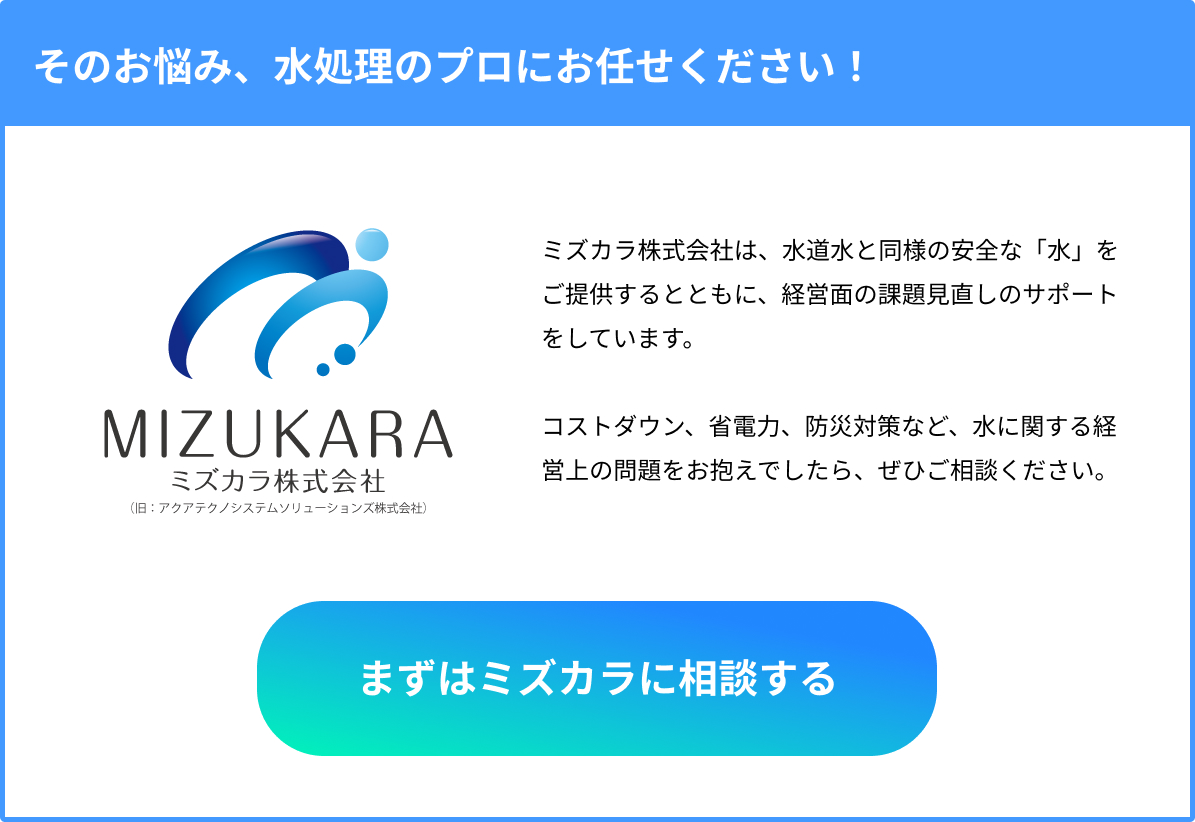目次
1. はじめに
工場や施設では「使う水(上水)」の確保に注力しがちですが、「捨てる水(下水)」の処理も同じくらい重要です。排水処理が不十分であれば、法規制違反や環境破壊、地域社会からの信頼低下など、企業にとって重大なリスクとなります。
この記事では、下水(排水)処理の代表的な方法とそのメリット・デメリット、さらにはコストや導入の工夫について詳しく解説します。
※当メディアの監修元であるミズカラ株式会社は、重金属・フッ素・ヒ素の排水処理に特化した『株式会社増澤技研』をグループ企業として有しており、専門性の高い情報提供に努めています。
▶株式会社増澤技研:https://atss.co.jp/masuzawa/
2. なぜ下水処理が重要なのか
日本では「水質汚濁防止法」により、事業場から公共用水域や地下へ排出する水に対して厳しい基準が設けられています。有害物質や過剰な有機物を含んだままの排水を河川などにそのまま放流すれば、環境汚染だけでなく、法的罰則の対象になります。
また、企業の社会的責任(CSR)やSDGsの観点からも、環境に配慮した排水管理は今後ますます重要性を増していくでしょう。
3. 下水処理の代表的な方法とその特性
3-1. 沈殿法
化学薬品を添加し、汚濁物質や重金属を沈殿・凝集させて除去する方法です。
- メリット:
- 比較的低コストで導入できる
- 操作が単純で保守が容易
- 重金属除去に有効
- デメリット:
- 処理後に汚泥(スラッジ)が発生し、処理や保管に手間がかかる
- 薬品コストが継続的に発生
3-2. 活性汚泥法
微生物の働きを利用して、有機物を分解・除去する生物処理の代表例です。
- メリット:
- 有機物の処理効率が高い
- 多くの排水に適応できる
- デメリット:
- 微生物の管理が難しい(温度・pH・酸素供給など)
- 運転停止やトラブル時の復旧に時間がかかる
3-3. 膜分離活性汚泥法(MBR)
活性汚泥法に膜分離を組み合わせた高度処理技術。高い処理精度と省スペース性が特徴です。
- メリット:
- SS(浮遊物質)や微細な病原菌も除去可能
- コンパクト設計が可能で、建築物の密集地や狭小スペースにも適する
- デメリット:
- 導入・運用コストが高くなる傾向がある
- 膜の目詰まり対策が必要
3-4. 逆浸透膜(RO膜)処理
概要:高圧で水を特殊な膜に通し、水分子以外を除去する物理的処理方法です。
- メリット:
- 高純度の水にまで処理することができる(再利用・リサイクルに適している)
- 重金属や塩類、微生物も除去可能
- デメリット:
- 設備投資・エネルギーコストが高くなる傾向がある
- 廃液(濃縮水)の処理が必要
3-5. 吸着法(活性炭やイオン交換樹脂など)
特定の物質を吸着材に取り込ませて除去する方法。重金属処理などに使われます。
- メリット:
- 選択的な処理が可能
- 操作が比較的簡便
- デメリット:
- 吸着材の交換や再生コストなど、ランニングコストが発生
- 処理能力に限界あり
4. 処理方法の選定ポイント
排水の性状(成分・濃度・温度など)や排出量、施設スペース、コスト、運用体制に応じて、最適な処理方法は変わります。以下のような観点で総合的に判断することが求められます。
- 処理対象(有機物なのか、重金属なのか、それとも油分なのか、など)
- 初期費用とランニングコスト
- 設備の設置スペースや作業員のスキルレベル
- 法規制を満たしているか
5. 処理水のレベルと用途
排水処理の目的は、単に「捨てるため」ではありません。現在では、処理水を再利用するケースも増えています。
| 処理レベル | 水の用途 | 処理技術の例 |
| 一次処理 | 排水管への放流前処理 | 沈殿法など |
| 二次処理 | 河川・下水道放流 | 活性汚泥法 |
| 三次処理 | 再利用・洗浄・冷却等 | MBR、RO膜、吸着法 |
6. 下水処理における今後の展望
近年では、省エネ型の水処理技術、AIやIoTを活用した水質モニタリング、省薬品化など、水処理技術におけるトレンドが加速しています。オンサイト方式やリース方式など、初期投資を抑えた導入手段も増え、また、企業の環境報告書やサステナビリティレポートでも排水処理の取り組みが求められるようになってきていることからも、より多くの中小企業でも高度処理の導入が進むことが予想されます。
7. まとめ
「使う水」を大切にするのと同じくらい、「捨てる水」にも責任を持つことが、これからの企業活動には欠かせません。処理方法にはそれぞれ特性があり、目的やコストに応じた選択が必要です。
排水処理はコストではなく「未来への投資」として捉え、持続可能な環境づくりに貢献していきましょう。
下水の最適な処理方法についてお悩みの際は、ぜひご相談ください。