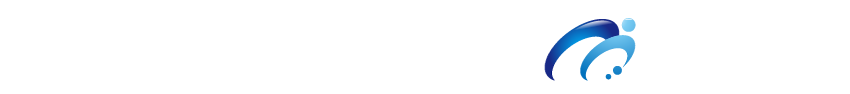目次
水道料金の値上がりの動き拡大始まる
〜上がり続ける水のコストと向き合うために〜
2025年現在、水道料金の値上げが全国で広がりを見せています。水は、電気・ガスと並ぶ重要インフラの一つ。生活インフラであると同時に、製造業・サービス業・医療福祉など、あらゆる産業に欠かせない存在です。
その「水」の価格が上がり続けているという現状は、企業にとって深刻な課題と言えます。
※本記事は、2019年6月27日公開の「3分でわかる!水道料金値上がりの実態とそのワケ」をベースに、現在の情勢を元に再編集したものです。旧記事はこちら。
直近10年間の水道料金の推移
まずは直近10年間の値上げ幅について触れてみましょう。
10年間で 150円~220円/月 の値上がり。年間では 1,800円~2,600円程度の負担増となっています。
これは一般家庭での水道使用量を参考にした試算ですが、
水を多く使う工場や、商業施設、医療施設などは、今後ますます大きなダメージを被ることは容易に予想できますね。
なぜ水道料金は高騰し続けるのか
水道料金の高騰には、大きく2つの背景があります。
安全・安定供給を維持するためのインフラ投資
老朽化した水道管の更新、耐震化などの防災対策、新規設備の整備といった取り組みは喫緊の課題です。
特に大規模地震が想定される日本では、断水リスクを最小限に抑えるためにも、耐震管への切り替えや管路整備が必要不可欠です。
しかし、その費用は膨大であり、水道事業者の多くが水道料金を財源として捻出しています。
節水の進行と人口減少による「収入減」
節水意識や技術の普及、人口減少により、水の使用量自体が減少しています。
これは環境面では望ましい動きですが、収益が減少する水道事業者にとっては経営を圧迫する要因になります。結果として、維持費を補うために水道料金の引き上げが続いているのです。
現状の水道料金では水道施設の維持費を賄うことが難しく、水道料金の値上がりという形で収支を合わせる必要が出てくるのです。
地域格差の拡大と中小施設への影響
地方では都市部に比べ、人口の減少が著しく進んでおり、1人あたりの負担も増加傾向にあります。
特に中小規模の工場や介護施設、ホテル・旅館などでは、地域差による水道料金の上昇が経営を圧迫するケースも出てきています。
今こそ「水の自立化」を検討する時
これからの企業に求められるのは、「水を買う」だけの時代から、「水を創り・管理する」時代への転換です。
私たちミズカラ株式会社では、水道料金の高騰リスクに備えた自家水道(オンサイト型地下水利用)ソリューションをご提案しています。
敷地内に地下水を汲み上げ、用途に応じて浄化・供給
水道料金の削減だけでなく、災害時の水源確保にも有効
水質分析から設備設計、行政申請までワンストップ対応
導入後、水道料金を数十%削減した事例も多数あります。
また、水道インフラへの依存を減らすことで、BCP(事業継続計画)対策にもつながります。
水道料金の値上げは今後も避けられない流れです。
だからこそ、「水コストの見直し」と「持続可能な水利用」の両立が求められています。
ミズカラでは、施設ごとの水使用量や用途、立地条件に応じた最適なソリューションをご提案いたします。
ぜひ一度、貴社の水利用状況についてご相談ください。