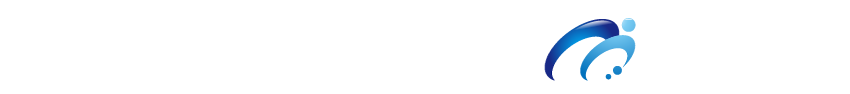私たちが日常的に利用する温浴施設や商業ビル、病院、介護施設などには、快適性や機能性だけでなく、高い衛生管理が求められます。とりわけ水まわりは、給湯・冷却・加湿といった形で施設全体に行き渡っており、その管理は多くの現場で厳格に行われています。
しかし一方で、わずかな管理ミスや想定外の設備劣化が引き金となり、感染症などの健康被害につながるケースも依然として報告されており、施設管理におけるリスク対応の重要性は今なお高い水準で求められているのが現状です。
特に注意を要する感染症の一つが「レジオネラ症」です。1970年代から公衆衛生上の重大な課題とされてきたこの疾患は、現在に至るまで空調設備や温浴施設を介して発症する事例が後を絶ちません。
実際、厚生労働省の統計によれば、日本国内のレジオネラ症の報告件数は年々増加傾向にあり、2024年には過去最多の2,400件超を超えています。(レジオネラ感染者数:https://www.suirikyo.or.jp/information/legionella-year2024-52.pdf)
高齢者施設や病院だけでなく、銭湯やスーパー銭湯などの入浴施設、ホテル・旅館のお風呂など、一般市民が日常的に利用する施設での感染も報告されており、従来以上に綿密な水質管理と予防策の徹底が求められるようになっています。
この記事では、レジオネラ属菌の基礎知識から、実務として取り組むべき水処理管理、そしてリスク対応のポイントまで、施設管理者や事業者の視点で解説します。
目次
レジオネラ属菌とは?その特徴と感染メカニズム
レジオネラ属菌は自然界にも広く存在し、特に温水・循環水・冷却塔などの「ぬめり」に棲みつきやすい菌です。
感染は、菌を含む水の微細な飛沫(エアロゾル)を吸入することで起こります。
例えば、以下のような設備は注意が必要です。
- 循環式の温浴施設・ジャグジー
- 加湿器・シャワーヘッド・噴水
- 空調冷却塔(クーリングタワー)
- 高齢者施設の機械浴や特殊浴槽
- 病院やリハビリ施設の水療設備
主な症状とリスク層
レジオネラ症は、次の2つの症状型に分類されます。
| 病型 | 概要 |
|---|---|
| レジオネラ肺炎型 | 重篤化すると呼吸困難や意識障害を起こし、死亡例もある。 |
| ポンティアック熱型 | インフルエンザ様の症状(発熱・筋肉痛など)。通常は軽症で回復。 |
特に高齢者、免疫力の低下した人、持病のある人(糖尿病、COPDなど)は重症化リスクが高く、医療・福祉施設での感染拡大が懸念されています。
なお、レジオネラ菌は人から人への感染は確認されていません。しかし、施設管理の不備が原因でクラスター化することがあり、事業者の責任が問われるケースもあります。
水処理管理の「盲点」としてのレジオネラ対策
レジオネラ菌は、単なる衛生問題ではなく、命に関わるリスク管理の対象です。加えて、目に見えないため、対応を怠ると「気づいたときには感染が起きていた」という事態に陥りやすいのが特徴です。
厚生労働省が発行する「レジオネラ症防止指針」(最新版:2022年改訂)では、以下のような管理ポイントが明示されています。
施設管理者が取り組むべき具体的な対策
循環水系の管理
- 残留塩素濃度:0.4mg/L以上を維持
- 月1回以上の水質検査(一般細菌・レジオネラ属菌)
- 週1回以上の系統洗浄と定期的な濾材交換
冷却塔(クーリングタワー)の管理
- 汚れ・スライム(ぬめり)除去と薬剤管理
- 飛散防止構造の採用
- 年2回以上の系統点検・清掃
加湿器やシャワー機器の清掃
- 使用後の水抜きと乾燥
- 月1回以上の消毒作業
点検記録の保存と整備
- 管理台帳や点検記録を3年間保管
- 保健所の立ち入り検査に備えた整備が必要
法制度による義務化も
多くの施設では、次のような法律・制度によって定期的な水処理と衛生管理が義務付けられています。
| 法令 | 適用対象 |
|---|---|
| 建築物衛生法 | 床面積3,000㎡以上の特定建築物(病院、百貨店、ホテル等) |
| 公衆浴場法 | スーパー銭湯・温泉施設など |
| 旅館業法 | 宿泊施設の大浴場・浴室等 |
| 感染症予防法 | 施設で感染症が発生した際の報告義務 |
これらに違反した場合、行政指導・施設名公表・営業停止処分等のリスクもあり、施設側の信頼に大きく関わります。
感染が発生したらどうなるのか?―事業者リスクと対応の実情
実際、過去には以下のような事例が報告されています。
- 某温泉施設(関東地方):レジオネラ症で死亡者が出たことで、保健所による調査と営業停止処分。約3週間の休業により数千万円の損失。
- 高齢者施設(関西):機械浴槽の衛生管理記録がなく、行政指導。以降は委託管理業者による水質管理体制を導入。
感染が疑われた場合、事業者には以下のような対応が求められます。
- 利用者への事実説明
- 保健所への感染症発生届の提出
- 感染源の特定と再発防止策の提出
- 施設内消毒・再検査・営業再開までの管理計画の提出
レジオネラの特徴の中で、最も重要な事を挙げるならば、対応を誤ると死に至ることもある深刻な感染症であるという点です。
たとえば食中毒のように一過性の体調不良で済むものとは異なり、感染が重篤化すると肺炎を起こし、最悪の場合は命を落とすリスクもあるのです。
そのため、行政も施設管理者に対して厳格な維持管理を求めており、感染の恐れがある施設名を公表して注意を促すなど、積極的な対策が取られているのです。
水処理会社との連携がカギ
最後に強調しておきたいのが、水処理のプロフェッショナルとの連携です。
管理の内製化には限界があります。専門的な設備や薬剤管理、細菌検査は、定期的に水処理会社へ依頼することで、精度の高い維持管理が可能になります。
また、水処理会社と連携して以下のような取り組みを進めることも推奨されます。
- 年間の清掃・薬注・検査スケジュールの作成
- 平時の教育・訓練(対応手順の整備)
- 異常時対応の連絡体制の構築
- 最新の指針・法改正の情報共有
感染症リスクは「管理の質」で防げる
レジオネラ症は、適切な水処理と設備管理により防ぐことができる感染症です。しかし、知識不足や油断が重なれば、重大な事故や施設の信頼失墜にもつながります。
繰り返しになりますが、レジオネラ症は死者が出るケースもある深刻な感染症です。だからこそ「たまたま無事だった」ではなく、「仕組みとして安全であること」が求められます。
施設管理者として、万が一の事態にも落ち着いて対応できるよう、水処理業者と連携しながら、日頃からシミュレーションや管理体制を整備することが重要です。
それは、施設における“品質保証”であり、社会的責任の一環でもあると、私たちは考えます。