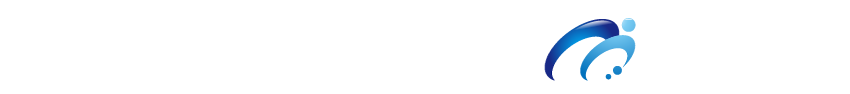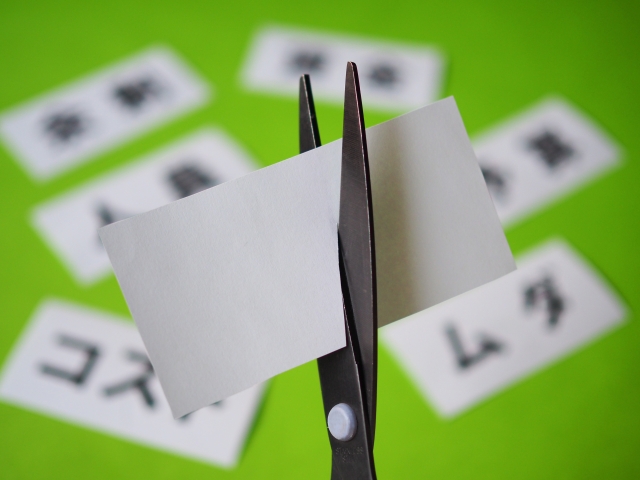工場経営に関わる経費を抑えるためには、どのような方法があるでしょうか。
「電気」「ガス」「通信」「水道」といったインフラに関わるコストは必ずかかってきます。
電気は2016年から、ガスは2017年から自由化され、さまざまな企業がこれらのエネルギーを提供できるようになりました。たとえば、ガス会社の大阪ガスや通信事業者のソフトバンクが電気を販売し、電力会社の関西電力が「関電ガス」としてガスの供給を始めています。
これにより、「電気とガス」や「電気とインターネット回線」といったセット契約によって、光熱費を抑えることができるようになりました。特に光熱費の使用量が多い法人にとっては、大きなコストダウン効果が期待できます。
一方で、唯一自由化されていないライフラインが「水道」です。2025年現在、水道は水道法に基づき、水道局からしか購入できない仕組みとなっています。
しかし、だからといって水道料金の削減をあきらめる必要はありません。たとえば、用途に応じて上水道から地下水への切り替えを検討することで、水道料金を大幅に削減できる可能性があります。 特に大量に水を使用する事業所では、地下水の活用によってコストと水資源の両面で大きなメリットを得られるケースも少なくありません。

※本記事は、2018年7月2日公開の「コスト(経費)とは?工場経営の経費削減で効果的に利益をUPさせる3つの方法」をベースに、最新の省エネ事例や技術情報を追加・再編集したものです。旧記事はこちら。
水道料金で経費削減を実現するには
その唯一の方法とは、「井戸を掘削し、地下水を利用する」という手段です。
地下水は自然に蓄えられた資源であり、その利用に水道料金のような費用は発生しません。つまり、水そのものは“無料”で使うことができます。さらに、地下水はその土地の所有者に帰属するという原則があるため、外部の供給に頼らず、自らの敷地内で独自の水源を確保できるという大きな利点があります。
特に、上水道料金が高額な地域や、大量の水を日常的に使用する施設──たとえば食品工場、病院、クリーニング工場、宿泊施設など──では、地下水を活用することで上水道の使用量を大幅に削減でき、結果として電気代やガス代以上のコスト削減効果が期待できます。
しかし一方で、地下水には注意すべき点もあります。
地層や地域によって水質は異なるため、地下水をそのまま業務に利用できるケースは限られます。たとえば、鉄分やマンガン、硝酸態窒素といった成分が基準値を超える場合、飲用や製造用途では使用できません。
そのため、用途に応じたろ過や浄水処理の設備を設置し、水質を安定的に確保する必要があります。
この処理に必要なろ過装置や除菌システムの導入には、初期投資としての設備費や工事費が発生します。地下水の利活用には、このようなコストと水質管理の必要性を十分に理解したうえで、適切な設備設計と維持管理体制を整えることが重要です。
オンサイト方式での井戸の掘削や、ろ過設備の導入
こうした課題を踏まえ、当社では、“オンサイト型”地下水活用ソリューションをご提案しています。
これは、お客様の施設内に専用の井戸を掘削し、用途に応じた最適なろ過・浄水設備を一括で導入するサービスです。設計から施工、導入後の運用・保守管理までをトータルでサポートするため、お客様側の手間やリスクを最小限に抑えながら、安定した地下水の利活用を実現できます。
特に当社の強みは、過去の豊富な実績とデータに基づく水質診断・処理設計のノウハウにあります。食品工場や医療施設、福祉施設、工業用水など、さまざまな業種・用途に対応した導入事例があり、それぞれのニーズに合ったオーダーメイド型のシステム提案が可能です。
また、導入前には事前調査として簡易的な水質検査と地下水ポテンシャル調査を行い、「その土地で地下水利用が可能かどうか」「どの程度の水量が確保できるか」などを丁寧に評価します。この段階で十分な効果が見込めると判断された場合のみ、具体的な設計・施工へと進みます。
初期投資こそ必要ではありますが、長期的に見れば月々の水道料金を削減でき、トータルコストで大きなメリットを享受できます。さらに、BCP(事業継続計画)の観点からも、上水道に依存しない“自前の水源”を持つことは、災害時のリスク分散としても高く評価されています。
地下水という資源を、経済的かつ持続可能な形で有効活用してみませんか。
私たちは、お客様の施設特性や使用水量に合わせた最適なプランをご提案いたします。