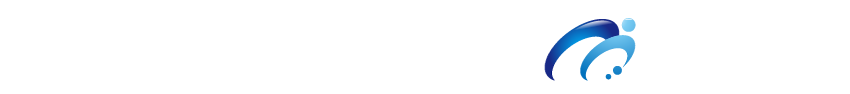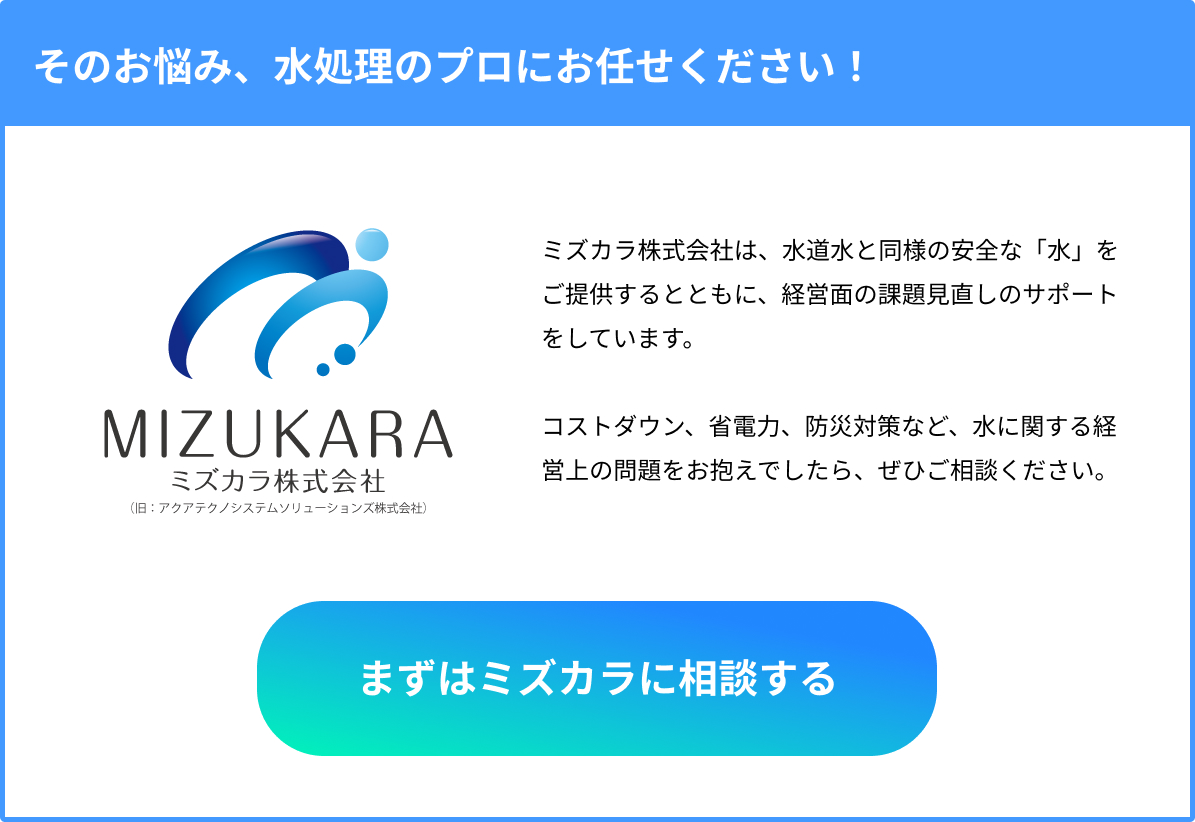近年、地震や台風などの大規模な自然災害が頻発し、防災対策の重要性、緊急性が高まっています。
その中でも注目されているのが「災害用井戸」の導入です。地下水を活用した井戸は、災害時の水の供給源としてだけでなく、企業のブランド価値向上や地域貢献の手段としても有効です。
※本記事は、2019年6月10日公開の大阪北部地震から1年。高まる防災意識に企業はどんな対策ができるのか?をベースに、最新の省エネ事例や技術情報を追加・再編集したものです。旧記事はこちら。
目次
地震などの災害時に、特に復旧が遅れる「水」
災害時の大きな課題として、電気やガスと並び、水道の復旧の遅れが深刻です。
実際に、2018年に発生した大阪府北部地震では、多くの地域で断水が発生し、一部では完全復旧までに1週間以上を要しました。
避難生活を送る住民にとって、水の確保は生活に直結する深刻な問題です。
加えて、近年の災害傾向を見ると、地震に限らず集中豪雨や台風によるインフラ損傷でも、長期的な断水が発生しています。
例えば、2020年の熊本豪雨では、山間部の水道管が流され、住民が給水車に頼る生活を強いられました。このような背景から、水の備蓄や代替水源の整備が社会全体の課題として浮上しています。
このような状況下で、地下水を活用した災害用井戸(地域によっては「防災井戸」などの名称が使われていることもあります。)は重要な代替水源となります。
国土交通省が策定した「災害時地下水利用ガイドライン」でも、地下水の活用が災害時の水供給確保に有効であるとされています。
地下水を活用した災害用井戸の設置が全国的に進んでいる
全国の自治体では、災害時に備えて地下水を活用した災害用井戸の設置が進められています。
例えば、大阪府では、災害時に近隣住民が井戸水を利用できるよう、井戸所有者と使用協定を結ぶ「災害時協力井戸」の制度を導入しています。
災害時協力井戸の登録は、約1,400箇所にのぼり、防災意識の高まりを感じられます。
参考:大阪府:災害時協力井戸について
また、全国の自治体のうちおよそ30%が、何らかの形で災害用井戸の整備や活用を進めていることが明らかになっています。
公的セクターだけでなく、企業や個人の協力によって、地域単位での防災ネットワークが形成されつつあります。
参考:内閣官房水循環政策本部事務局 災害用井戸施策実態調査結果
企業防災としての水源の確保
昨今では、民間企業が防災対策やBCP対策として地下水を活用した水道設備(井戸)を導入し、
自身の施設の第二水源として備えると同時に、災害時には地域住民に水を提供するというような取り組みもあります。
例えば、当社が専用水道設備の新規導入の際、携わった大阪府内にある商業施設では、
- 水道料金の削減
- 災害時における断水対策
として地下水を活用した井戸を新規で導入いただきましたが、
地域の指定臨時避難場所として市の防災マップにも記載されており、地震などの有事の際の水源として利用することができるため、
地域貢献としての役目も果たしています。
企業の社会的責任としての防災インフラ整備
災害用井戸の導入や第二水源の確保は、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みとして、企業ブランディングの強化にも寄与することが期待されます。
SDGsにおいては、下記の3つの目標の達成に貢献すると考えられます:
目標6「安全な水とトイレを世界中に」:災害時の水源を確保しておくことで、災害時であってもより多くの人へ安全な水を届けることが可能に。
目標11「住み続けられるまちづくりを」:地域のレジリエンス(回復力)を高めるインフラ整備。
目標13「気候変動に具体的な対策を」:気候変動により増加する自然災害への対応の強化。
災害時に従業員だけでなく、地域住民の安全を確保する体制を整備することは、企業としての信頼性を高め、ステークホルダーからの評価を向上させるでしょう。
重要性が増す企業防災の今後の展望
災害用井戸の導入や施設の第二水源の確保を検討する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
- 地下水の水質と水量の確認:飲料水として利用することを想定している場合には、定期的な水質検査を行い、安全性を確認する必要があります。
- 設備の維持管理:定期的な点検やメンテナンスを行い、災害時に確実に稼働する体制を整備します。
- 自治体との提携も活用:既に記述したように、「災害時協力井戸」の登録を呼びかけている自治体も多くあり、また大規模な施設であれば地域の「指定緊急避難所」としての役割を担うこととなる場合もあるでしょう。災害時に地域住民への水の提供を行う場合、自治体との協定の締結も検討し、協定した際には役割分担や連携体制を明確にします。
- 情報の周知:災害用井戸の存在や利用方法について、従業員や地域住民に周知し、災害時に円滑に活用できるようにします。
今後、気候変動の影響などにより、自然災害のリスクが高まる中で、企業防災や災害用井戸の重要性はさらに増すと考えられます。
企業が災害用井戸を導入し、地域社会との連携を強化することは、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。
災害用井戸は、「防災」「地域貢献」「ブランディング」の3つを同時に実現できる重要なツールです。
ぜひこの機会に災害用井戸の導入を検討いただき、企業の社会的責任を果たすとともに、地域社会との共生を目指していただきたいと思います。