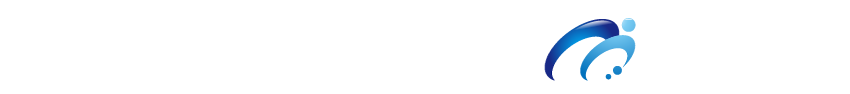皆さんは、2015年に国連サミットで採択された「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」をご存知ですか?
SDGsとは Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標) のことで、気候変動の深刻化や資源の枯渇、生物多様性の損失など、地球規模の課題に対して、2030年までに達成すべき目標を掲げています。
今や、こうした課題は私たちの暮らしやビジネスにも直結しており、カーボンニュートラルやエネルギーの安定供給は喫緊の課題となっています。
このような背景のもと、日本でも政府をはじめ、多くの企業、自治体、教育機関がSDGsの理念に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを加速させています。
とくに製造業の分野では、環境負荷を軽減しながら経済性も高める「省エネ」や「再生可能エネルギーの導入」などの取り組みが注目されています。
SDGsの目標を達成するためだけでなく、こうした環境配慮の取り組みは、エネルギーコストの削減や企業価値の向上といったメリットももたらします。
今回は、環境に配慮した工場で省エネを実現した事例4選をご紹介します。
「持続可能なものづくり」のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
※本記事は、2018年7月2日公開の「環境に配慮した工場で省エネを実現した事例4選」をベースに、最新の省エネ事例や技術情報を追加・再編集したものです。旧記事はこちら。
目次
SDGsから見る企業に求められること

SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連サミットで採択された「持続可能でより良い世界」を実現するための17の国際目標です。2030年の達成を目指し、環境・社会・経済のあらゆる分野で、国や企業、市民が一体となって取り組みを進めています。
日本では、2018年に政府が「SDGsアクションプラン」を策定し、国の強みや地域特性を生かした「日本型SDGsモデル」の発信を強化してきました。2025年現在、その取り組みはさらに進化し、地方創生や脱炭素化、デジタル技術の活用を通じた新たな価値創出にもつながっています。
アクションプランの中心には、SDGs実施指針に基づく8つの優先課題が掲げられており、特に「省エネ・再生可能エネルギーの推進」「気候変動への具体的な対応」「循環型社会の構築」といった分野は、産業界にとって喫緊の課題です。エネルギーコストの高騰や資源制約、ESG投資の加速といった背景もあり、持続可能な経営戦略の中核として、これらのテーマに真剣に向き合う企業が増えています。
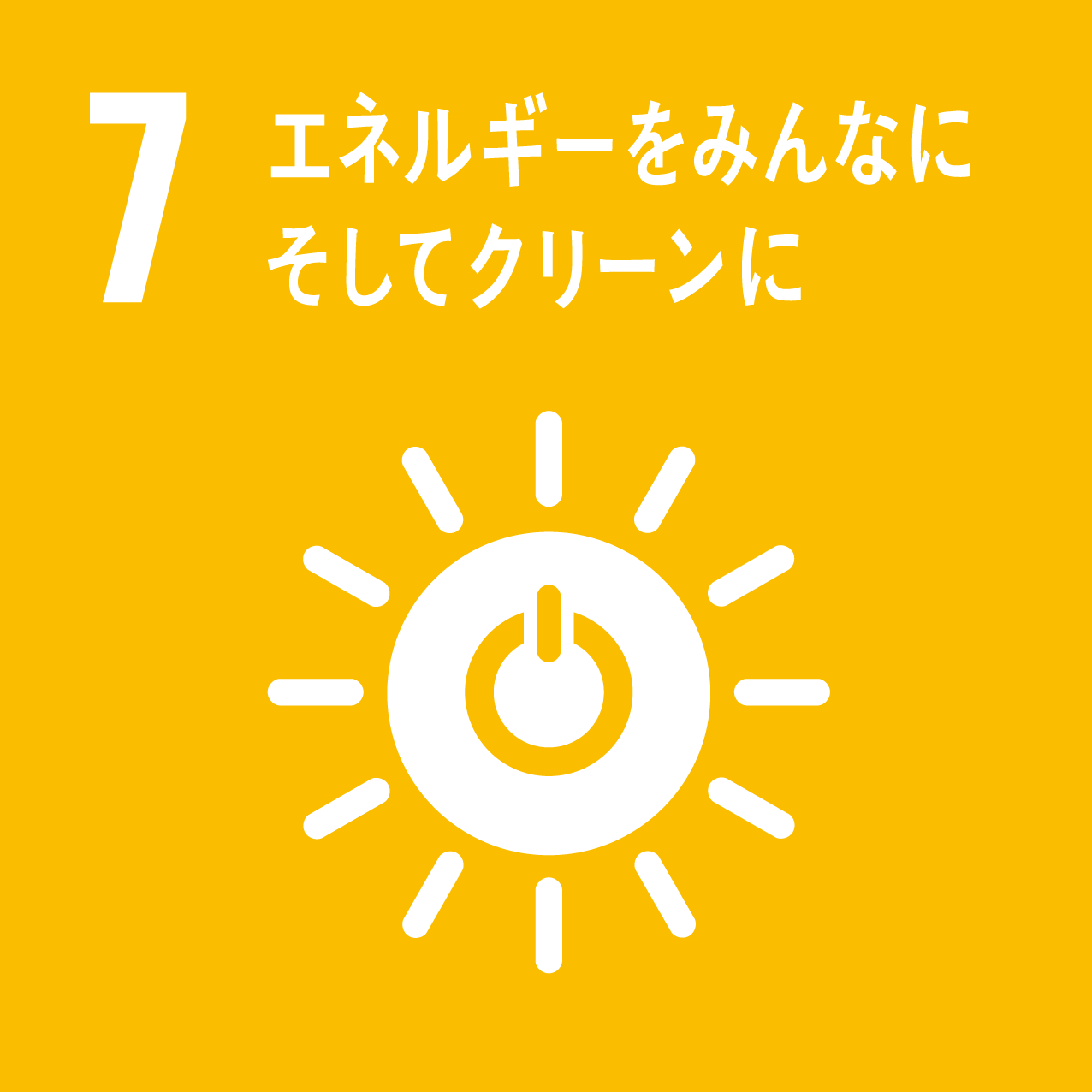


日本政府は、SDGs達成およびカーボンニュートラル社会の実現に向けた柱の一つとして、「徹底した省エネルギーの推進」を掲げています。これは、企業や住宅部門を含む幅広い分野において、効率的なエネルギー利用を加速させることを目的とした取り組みです。
2025年現在、以下の3つの施策が特に注目されています。
業界別のエネルギー削減目標設定と自主的な省エネ推進
各業界が自主的にエネルギー効率向上の目標を掲げ、省エネ活動を実行。省エネ診断や管理体制の強化が進められています。次世代冷凍・空調技術の最適化と評価手法の開発
インバータ制御や自然冷媒を活用した高効率機器の普及に加え、その性能を客観的に評価する新たな指標の整備が進んでいます。NZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及促進
住宅部門では、断熱・高効率設備・創エネを組み合わせたZEHの導入が加速。自治体や民間事業者による地域単位での導入事例も増えています。
これらの施策は、2030年度までに2012年度比でエネルギー消費効率を35%改善するという政府目標の達成に向けて位置づけられており、法制度面の支援も充実しています。
具体的には、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」および「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が改正・強化され、企業に対するエネルギー使用状況の把握・報告義務や省エネ計画の提出義務が拡充されています。
さらに、省エネ投資を後押しする各種補助金制度も展開中です。
主な支援内容の例:
老朽化設備の高効率機器への更新支援(工場・オフィス等)
ZEH(ゼロエネルギー住宅)建設やリフォームへの補助
高性能断熱材や省エネ建材の導入支援
実証事業を通じた先進的省エネ技術の普及促進
これらの政策は、企業にとってコスト削減と持続可能性の両立を実現する有効な手段であり、エネルギー価格が高止まりする2025年においては、ますますその重要性が増しています。
参考:環境省 SDGs 「SDGs実施指針」優先課題⑤
企業が特に配慮すべき環境問題とは
企業活動と環境保全は、今や切り離せない関係にあります。特に製造業・工場を有する企業にとっては、環境への影響を最小限に抑える取り組みが、社会的責任(CSR)やESG経営の一環として強く求められるようになっています。
その中でも注目すべきなのが、産業廃棄物の適正管理です。製品の製造過程で廃棄物の発生は避けられないものですが、それを「どのように抑制し、処理・再利用するか」が企業の環境意識を問われるポイントとなります。
2025年の今、求められているのは単なる法令遵守ではなく、資源循環の視点を取り入れた持続可能な運営体制です。たとえば、排出物の再資源化やリサイクル工程の内製化、排水の再利用、エネルギー回収といった取り組みが評価される時代になっています。
ダイオキシンの発生
廃棄物の焼却やパルプの漂白、化学物質の製造により発生します。難分解性であるため、土壌や水に残されやすく、生体に影響を及ぼします。
参考:埼玉環境化学国際センター
「ダイオキシン」ってどんな物質?
大気汚染
塗料やインクの溶剤に含まれるVOC(有機化合物)は、大気中に気体になる物質で、光化学スモッグなどの原因になっています。
参考:独立行政法人 環境再生保全機構
主な大気汚染物質と人体への影響
水質汚染
工場からの排水が河川に流れ出ることにより、水質が汚染されます。
以前は工場排水が主な原因でしたが、現在は生活排水も水質汚染の要因の1つとされています。
参考:愛知県
川や海の汚れの主な原因は何ですか?(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)
アスベスト問題
以前、アスベスト(石綿)は、工場・ビルの保温断熱材や防音材、ブレーキパッドとして壁に吹き付けて利用されるなど、盛んに使われていました。
現在は、アスベストに肺がんを引き起こす可能性があると報告されているため、使用や製造は原則禁止されています。
参考:厚生労働省
アスベスト(石綿)に関するQ&A
環境に配慮した工場で省エネを実現した事例5選
では、環境に配慮すれば効果はどのようなものが得られるのでしょうか。
大手企業で環境に配慮した工場の実際の事例をご紹介します。

水質汚濁防止
株式会社 浅野歯車工作所
油水分離槽の配置を見直すともに、浮上油回収分離装置を設置し、流出リスクの低減に努めています。
私たちは製品開発力と生産技術力を駆使した「徹底したムダ排除」により、地球環境への負荷低減に努めています。製品の小型・軽量化と高効率化、生産性改善活動、不良の出ない工程づくりは、環境保全活動の重要な取り組みです。
引用:株式会社 浅野歯車工作所
環境マネジメント
CO2排出量の削減
アサヒビール
全工場でビール類の自社製造に必要な年間使用電力量のうち自家発電を除いたすべてをグリーン電力を使用。
ビールを製造時、釜の工程をホップと麦汁の別々で行う技法を開発し、CO2排出量を約30%削減しています。
参考:アサヒビール
環境に対する取り組み
地球温暖化対策
三菱製鋼株式会社
千葉製作所では、経年劣化した水槽制御盤の更新とともに、冷却水循環ポンプのインバーター化を行いました。
圧力制御で電動機の回転数を制御し、電力を削減する事でCO2排出の低減を図っています。
他にも、室蘭製作所では、熱効率の高い省エネタイプのリジェネバーナーへ更新したことにより、製鋼工場の燃焼ガス使用量は、従来比12%の削減を達成しています。
2015年度のCO2排出量は、国内事業所計で17万4千トンとなり、2005年度の29%減となりました。
引用:三菱製鋼株式会社
CSR情報 環境報告
大気・水質・土壌の汚染防止
三菱ケミカル株式会社
三菱ケミカルは、多種多様な化学物質を取り扱っていることから、排ガス・排水処理設備の導入・改善による有害大気汚染物質の排出量削減や、公共水域への汚染物質の排出量削減に、継続的に取り組んでいます。
大気、水質への環境負荷物質(NOX、SOX、ばいじん、COD)の排出量は、低減もしくは維持しています。2017年度は、組織改編などの要因によりNOXが900トン減少しました。
引用:三菱ケミカル
レスポンシブル・ケア活動 環境保全
また、環境保全活動による経済効果も公表されており、
- リサイクルにより得られた収入額
- 省エネルギーによる費用削減額
- 省資源で得られた収入額
を合わせた額は、260億円を超えています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
近年、気候変動や資源枯渇などの地球規模の課題が深刻化する中、企業に対する環境対策の要求は国際的に一層強まっています。ESG投資の拡大やグローバルサプライチェーンにおける環境基準の厳格化により、環境配慮はもはや選択ではなく、企業価値を左右する前提条件となりつつあります。
日本国内でも、政府はSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向け、脱炭素・資源循環・生物多様性保全など多岐にわたる施策を展開しており、民間企業との連携による社会変革が加速しています。
このような中、今こそ自社の環境対策に取り組む絶好のタイミングです。省エネルギー機器の導入や廃棄物の適正管理、水使用量の見直しなど、身近な改善策の積み重ねが、最終的には光熱費削減や企業イメージ向上といった実利につながります。
ちなみに、当媒体を運営する当社「ミズカラ」でも、「ATSSのSDGsアクション」として、SDGsの達成に向けた具体的な取り組みを強化しています。水資源の有効活用や省エネ技術の導入支援を通じて、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
※本記事は、2018年7月2日公開の「環境に配慮した工場で省エネを実現した事例4選」をベースに、最新の省エネ事例や技術情報を追加・再編集したものです。旧記事はこちら。
最後に
当ナビを運営しているミズカラ株式会社は、様々な水処理のご相談を承っています。
「水に関わるコストを抑えたい」
「水処理設備の効率化をはかりたい」
「水管理の省力化について相談したい」
「第三者から見た水管理の診断をお願いしたい」
お考えの企業様、工場、病院、商業施設の管理者の方など、この機会に下記より、お気軽にご相談ください。